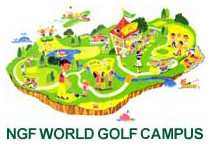いま世の中がにわかにTPPと騒がしくなってきた。グローバル化が進む中、貿易の自由化を進めて物資やサービスが自由に取引できるようにしようということで、私たち庶民からすれば「えっ!いまさら」という気がする。総理大臣も「平成23年を開国元年にしよう」といって拳を振りかざしているが、昨年一年間にわたって大河ドラマで幕末明治維新の姿を観てきた私たちは、「えっ!いまさら開国?」という素朴な疑問が湧いてくる。
そういう私も新年早々「2011年をゴルフ開国元年にしよう」とネット上で力説したものの、ほとんどの人が「えっ!いまさら」と思ったかもしれないという不安が起きてきた。高度情報社会に住んでいる私たちは、何でも知っていると信じていながら実は何も知らないのではないかという不安に変わってくる。
尖閣諸島事件で勇気ある情報公開がなければ、私たちは今も真相を知らないまま「中国と国交断絶しろ!」と拳を振り上げていたかもしれない。
私たちゴルフ好きは今も「小遣や年金で毎日ゴルフができたらなぁ」と夢を見続けている。欧米豪州カナダでは1000円前後でゴルフができるのに、何で日本では10倍もするンだろう。素朴な疑問を持つ人はまだいい方で、ほとんどの人は疑問すら持たない。つまり情報鎖国社会に住む私たちは世界の真相を知らされていないから、日本の現状を世界の姿と思い込んでいる。極東の島国に住む私たちは案外、世界の真相を知らされたくないのではないか。
ではゴルフ開国を叫ぶとどうなるだろう。TPPと同じように猛烈に反対する人たちが出てくるだろうか。「自由化反対!日本のゴルフ場を守れ」「合理化反対!ゴルフ場の雇用を守れ」「値下げ反対!プレーの安全を守れ」実にもっともらしい口実の反対運動が次から次へと沸き起こりそうな気がしてきた。小遣いや年金で毎日ゴルフができたらというささやかな夢は諸外国では当たり前でも、まだ日本では危険思想なのだろうか。
吉田松陰も坂本竜馬も外国に行ってみたいというささやかな夢を抱いて命を落とした。あれから140年も経ったから、もうそんなことは起きないだろうと思うが、歴史は繰り返すともいうから気をつけないと何が起きるか分からない。さすがに海外渡航は自由になったから、開国を叫んで命を落とすくらいなら、格安便を使って『海外ゴルフ三昧旅行』にでも出掛ける方が安全で安上がりかもしれない。
2010年度トーナメントシリーズが終了した。終ってみればそういうことかと思うことも、結末を見るまでは実にはらはらする。だから闘うものも観戦するものもエキサイトするし興行としても成り立つわけだ。最初から結果が分かっていれば、誰もお金や時間を使って観戦などしない。かくいう私だって今年度の賞金王は誰になるのか、水曜日からそわそわしていたことは否定できない。
そしてほとんどの人が石川遼か池田勇太のどちらかが優勝して今年度賞金王に輝く構図を画いていたのではないか。石川遼の連覇に期待しながらも、進境著しい池田勇太の優勝もありうる。勇太自身、相当意識して優勝宣言に近い発言をしていたから、なおさら多くの人が二人の優勝争いを予想していたはずだ。
天(神)の計画は大方の見方と異なり、最終戦優勝争いはアラフォー藤田寛之と谷口徹の一騎打ち。賞金王は韓国選手キム・キョンテに決定した。戦前の予想と異なり石川遼と池田勇太の名はなかった。最終戦は20歳前後の若手ホープ同士の一騎打ちに期待が寄せられたが、40過ぎのオヤジ同士の一騎打ちとなりました。藤田の優勝スピーチが印象的だ。「同世代に自信と勇気を与えられたら嬉しい」とは謙虚にして切実な言葉である。40代というのは社会的責任が重くのしかかる割に社会から軽くみられ、上からも下からもプレッシャーをかけられる辛い世代なのだ。私も過去の経験上、藤田の言葉が身にしみて分かる。
世の中はいつも矛盾に満ちていて、世界的景気低迷の中で20歳前後は就職難と失業に苦しんでいるし、40歳前後はバブル後遺症の責任だけを一身に背負わされている。石川遼や池田勇太の同級生たちは浪人となって最低賃金確保のため、足を棒にして毎日就職活動をしているだろう。藤田寛之や谷口徹の同級生たちは組織の中間管理者として、また一家の柱として身も心もすり減らして日夜働いているに違いない。これはトーナメントプロと一般社会人のどちらが楽な仕事かという比較の問題ではない。人生の選択の問題だから全て本人の取組姿勢に掛かっていて、結果責任は自分で負わなければならない点は同じだ。
韓国プロの成長は著しく、男女とも日本の賞金王を射とめた。彼らの日常姿勢からこの結果は予想できたが、現実を前に改めて考えさせられる。南北国境間にある一触即発の緊張感に包まれた日常生活は、いつ戦陣戦乱の渦に巻き込まれるか分からない。トーナメントに出場している今は二度と訪れないかもしれないし、来年はないかもしれない。韓国プロによる賞金王男女制覇の快挙に神の意思や天の采配を感じて厳粛な気持ちになったのは私一人ではないはずだ。心底から「おめでとう。今を大切に!」と祝福したい。
池田勇太が強くなってきた。強くなったばかりかアンちゃん風だった勇太に王者の風格が出てきた。人が地位をつくるのか、地位が人をつくるのか分からないがとにかく成長した。テレビに映る姿を見て日に日に惹かれていく。あの独特なスイングも魅力的に見えてくるだろう。
池田勇太のスイングは何処で身につけたか知らないが、米国ではジム・ヒューリック、日本では青木功と同系統である。かつて河野高明や草壁政治が採用していた通称「逆八スイング」といわれるスイング系統である。ビギナーやアベレージゴルファーにはインサイドに引いてアウトサイドに下ろしてくる「八の字スイング」が多いが、これは後ろからスイングプレーンを見ると八の字を描いているように見えるため、このように名付けられた経緯がある。これとは反対に「逆八スイング」はストレートに引いてインサイドに下ろしてくるから八の字が反対に描かれて逆八という訳だ。
30年ほど前、青木功が世界的プレーヤーになりだした頃、米国コロンビアカントリークラブのコーチで全米第一人者といわれたビル・ストラスバーグが「青木功こそ理想のスイング」と絶賛した。当時NGFアメリカセミナーの主任講師だったビルを日本にも招聘して東京・京都・大阪でセミナーを開いたが、200人以上受講して誰もこのスイングをマスターできなかった。ビルの言葉を借りれば「クラブを真直ぐ上げて、右脇を絞めるように引き下ろし、また上げる」と簡単にいうのだが、誰も巧くできなかった。セミナーに集まったトッププレーヤーたちはビルの講義を聴きスイングを見て「玄人芸」と絶賛したのだが。
ということは青木功も池田勇太も黒光りした玄人芸なのである。人知れず数限りない球を打ち続け、百戦練磨して磨き上げた達人名人のワザである。素人が簡単に盗んだり真似のできる芸ではない。恐らく本人も自分の技を伝えられるとは思っていないはずだ。「名選手必ずしも名コーチならず」の例えどおり、絶対といってよいほど名人芸は伝授できるものではない。子供は器用だから結構上手にスイングを真似するだろうが、経験や体験は最終的に真似したりバーチャルトレーニングによって身に付くものではない。
基本とは名人や達人に共通する原則を導き出し、その中から誰でも真似のできる普遍技術を体系的に整理したものである。だから基本はつまらなく退屈である。こんなこと猿でも真似できると思うことばかりだ。その基本をタイガー・ウッズも石川遼も毎日コツコツ練習しているという。これはまさに凄業だ。
2010年米国PGA公式戦が終了した。40歳のジム・ヒューリックがフェデックス・プレーオフシリーズ最終戦に優勝し135万ドルを獲得すると同時に年間総合優勝も決めて賞金1000万ドルも獲得した。ビジェイシン、タイガー・ウッズに次いで史上三代目だそうだがイヤハヤ驚きました。1年間でアメリカ大統領報酬の30年分を稼いだそうで、荒稼ぎ振りはハゲタカファンド顔負け。アメリカツアーも本来厳しい世界で、稼げないものはガソリンスタンドやコンビニエンスストアでアルバイトをしながら旅費を稼ぎ、安モーテルやキャンピングカーに泊まってツアプレーヤー(旅芸人)を続けている。だからギャンブラー(博徒)ともいう。プロトーナメントは生活を賭けた大バクチだから「勝者金満、敗者難民」「一将功成り万骨枯る」を地で行く優勝劣敗の世界だ。命懸けの真剣勝負だから観るものにとっては面白いが、決してアマチュアが見習ってはいけないゴルファーの姿でもある。昨年の覇者タイガー・ウッズは膝を壊し、家庭を壊し、ファンを裏切り、精神を病んだ。ゴルフは全てのスポーツの中でも唯一、人間の善意に全てを託している。善意とは礼節、誠実、正直、謙虚、寛容など人間が本来持っていないものを周囲に示す心だ。だから善意は教育され、忠告され、訓練されないと身に付かない。身についていないものを「付焼刃」というが、ちょっとしたことで簡単にこぼれ落ちてしまう存在でもある。
プロツアーを見ていて大変気がかりなことは、確かにプレーヤーは育っているがゴルファーが育っていないことで、カネ稼ぎに始ってカネ稼ぎに終るプロツアーのシステムは「勝者金満、敗者難民」の金融資本主義と同じシステムだ。だから、このままプロツアーがリーマンブラザースと同じようにバブル崩壊で終らなければよいがと思う。もうひとつ心配なことはアマチュアゴルファーがプロゴルファーを見習っていることだ。10代,20代の若者に闘争心を植え付けることは簡単だが、善意を育てることは時間が掛かる。アマチュアゴルファーが若いスタープレーヤーに憧れるのも結構だが、彼らは商業資本主義の広告塔であって使い捨て商品であることを忘れてはならない。私たちにとってゴルフは人生を豊かにする生涯スポーツそのものだし、青少年にとっては倫理道徳教育プログラムであることも決して忘れてはならない。昔から「ゴルフから得たものはゴルフに返せ」と言われてきた。でもゴルフから得るものは余りにも多過ぎて一生かかっても返しきれない。アマチュアゴルフには私たちの魂を健康にする「ゴルフマインド」という成分が含まれていて、多少の経済負担が伴っても余りある効能がある。アマチュアは間違っても精神を病んだり、魂を害するようなゴルフを見習ってはならない。
「何事も基本が大切」という言葉は頻繁に聞く割に、実際は結構おろそかにされているようだ。あのタイガー・ウッズですら、今は基本に戻ってスイング形成やパッティングドリルをやり直しているというし、石川遼も試合のあと「もう一度基本を徹底的にやります」とよく言っている。世界一や日本一を誇るトッププレーヤーといえども、基本のうえに高等技術が形成されていることを証明しているようだが、その土台となっている基本とは何かとなると、多くの人が沈黙してしまう。実は、ゴルフの基本は1970年代以降に確立したもので、それ以前にゴルフの基本はなかった。「えっ!ウソ」という人は比較的若い世代で、「ほんとだよ」という人は間違いなく中高年世代のはず。
1960年代に米国ゴルフ界は学校体育授業にゴルフを導入するためNGFの開発プロジェクトチームの手によって教育プログラムが開発されていた。学校教育に導入するには、どんな生徒にも当てはまる基本を確立しなければならない。
NGFコンサルタントといわれる大学コーチやPGAプロによって編成されたプロジェクトチームは、数年の歳月をかけてNGF教育プログラムを完成させた。いわば講道館の嘉納治五郎が柔道の基本を確立した話に似ている。米国の若手中堅プロは殆んど基本教育プログラムによって育ってきた。米国で育った選手のゴルフは生体物理原則に則ったワンスイング・スクウェアシステムから飛球法則に従った9種弾道を自在に打ち分けるスタイルなのですぐ分かる。
9月第三週、札幌で開催されたANAオープンの最終ラウンド池田勇太と韓国K.J.チョイの一騎打はとてもおもしろかった。池田勇太は日本の強者達に育てられた職人芸。K.J.チョイは米国で育った基本ゴルフ。「何としても勝ちたい」という思いはほぼ互角のようだがスタイルの違う両者が一歩も譲らないまま、とうとう18番最終パットまで決着がつかないという手に汗握る真剣勝負となった。K.J.チョイは厳しい米国ツアーを戦ってきた若手国際選手だし、池田勇太は日本が期待する若手ホープだ。本人もギャラリーも池田勇太に優勝させたい一心が勝負を決した感があるが、米国ツアーで鍛えられたマシーンのように正確なショットと冷静なマネジメントゴルフに、池田勇太がじりじりと追い詰められていることは誰の目にも分かった。K.J.チョイが18番、計測したようなセカンドショットをバーディーチャンスにつけて、池田勇太は喉元に刃物を突きつけられたような恐怖感を味わったはずだ。K.J.チョイがバーディパットを外したために、池田勇太は冷静さをとり戻して優勝できたが、優勝パットを決めた瞬間に勇太の目から溢れ出した涙が全てを物語っていた。プレーオフになったら限界まで追い詰められた池田勇太に勝ち目はなかったはずで、イヤというほど基本の恐ろしさを知った彼は、この優勝できっと大きく成長するに違いない。
ゴルフゲームは基本的にマッチプレーとストロークプレーしかない。マッチプレーは人と人の勝負で、ストロークプレーは人とコースの勝負だ。最近日本でマッチプレーをする人を殆んど見なくなった。イギリスでは今でもストロークプレーをする人は殆んどいないらしい。スポーツは全て誰かを相手に勝負するものだから、誰を相手に闘っているか忘れると勝負にならない。
実際にゴルフをしている人で、どれだけの人が闘う相手が誰かを認識しているかとなると甚だ疑問だ。私も含めてほとんどの人が自分と闘ってしまっているのではないか。もしそうでなければ、あんなに腹が立ったり情けなくなるはずがない。みんな自分に腹が立ち情けなくなるのだ。だってコースが相手だと承知の上でプレーしているし、コースは自分に何をした訳ではないことも良く分かっているから、結局は自業自得と諦めなくてはならない。それがしゃくの種なのだ。どんなに人格者といわれる人でも、目尻がつり上がったり唇をかみ締めたりするから、相当怒っているなと分っておかしい。「笑っちゃ悪いよ」と思うともっとおかしくなる。今でも20年も30年も前の出来事を思い出して一人で笑うことが時々ある。笑われた相手は今でも思い出して腹を立てているかと思うと、またおかしくなる。自分もきっと誰かに笑われているに違いないと思えば「おあいこ」ということで許されるだろう。
テレビで観ているとタイガー・ウッズと石川遼の顔が引きつっている。心中穏やかでないことがすぐ分かるほどだから、二人ともコースと無心に闘う心境ではないのだろう。タイガー・ウッズが心中穏やかじゃないことは良く分かるが、石川遼は何が原因だろう。付きまとうマスコミやファンか、コマーシャルの煩わしい仕事か。メンタルスポーツの代表のように言われるゴルフの世界で雑念は絶対禁物だが、二人には雑念が多すぎるのではないか。去年の二人の顔は輝いていたが、今年はいささかくすぶっている。最もタイガーは父親を失ってから心の支えを失ったせいか、王者の風格がなくなり些細なことに腹を立ててイライラしていることが良くあった。ゴルフが王者になれても人間はなかなか王者になれないことを証明しているようだ。
王者の風格というと野球のイチローと松井選手、相撲の白鳳、水泳の北島選手、ゴルフでは宮里藍に見られるようになった。風格ってナンだといわれると困るが、闘う相手を良く弁えて決して自分や他人に腹を立てず、少なくとも他人に悟られることなく、自分で解決できる人に備わるものなのだろう。聖書はいう「怒りを治めるものは勇士に勝る」と。でもエンジョイゴルファーにとっては「怒るも愛嬌のうち」と思っておおらかにゴルフを楽しみたいものだ。
私は永年ゴルフの世界にいながら「ゴルファー」と「プレーヤー」を意識的に区別してこなかったし、言葉の意味についても明確に定義してこなかった。
タイガー・ウッズや朝青龍の問題が起きて「はてな?」と真剣に考え出したのが正直なところだ。かつて「ゴルフ人口」を定義するのに「練習場ゴルファー」と「コースプレーヤー」と無意識に使い分けていた時期があるが、厳密に定義したわけではない。練習場にはコースに行った経験がない人も数多くいるだろうという意味で漠然と「練習場ゴルファー」といっていた。真面目に考えると「ゴルファー」と「プレーヤー」は明確に区別しなければいけない気がする。
普段ゴルフコースにはプレーする人しかいないから、全員プレーヤーといっても良さそうだし、全員ゴルファーといっても良さそうな気がするが、トーナメント会場となったコースでは、選手だけがプレーヤーでギャラリーはゴルファーも非ゴルファーもいる。最近、石川遼のまわりにはケータイカメラを持った「追っかけおばさん」がいっぱいいるが、どう見てもゴルファーには見えないもののコースに行った経験はある人たちだ。コースだけではなくテレビや雑誌の前にもゴルフの経験はないが、私以上にゴルフ界に詳しい人たちがいる。
インターネットの世界にはクラブもボールも触ったことがない「ゴルフオタク」が相当いるらしいが、実態については私もまだ良くわからない。このような人たちは「プレーヤー」ではないが「ゴルファー」と呼ぶべきだろうか。
国技館に行けば「相撲取り」と「相撲ファン」はすぐ区別できる。ちょんまげ結ってふんどしを締めてるいる人が「相撲取り」で、その他の人は全員「相撲ファン」だ。最近は「女性相撲ファン」がいっぱいいるが、ほとんどのひとが相撲経験はないはずで、横綱審議会の委員を務めた内館牧子さんだって相撲を取った経験はないと思う。でも内館さんの朝青龍に対する見解は立派で「アスリートとして尊敬できても横綱として認め難い」といって伝統を重視された。さすがに大学院で「大相撲の宗教学的考察」という論文を書かれただけのことはある。米国ゴルフ協会やマスターズ委員会がタイガー・ウッズに対して明確な見解を表明できなかったことに較べて実に立派だったと言いたい。
歴史と伝統のある日本の大相撲と歴史の浅い米国のゴルフとの差が歴然とした気がするが、本来なら英国に発祥するゴルフは大相撲以上の歴史と伝統をもっているし、宗教学的に考察したら「プレーヤーとしては尊敬できてもゴルファーとして認め難かった」はずである。マスターズ創設者のボビー・ジョーンズはプレーヤーである以前に、キリスト教騎士道精神を持った立派なアマチュアゴルファーとして聖人の冠を付された人だからである。
2010年4月18日サウスカロライナ州ハーバータウン・ゴルフリンクスで開催されたPGAツアー「ベリゾンヘリテージ」最終ホールで素晴らしいプレーが見られた。13アンダー同士でプレーオフになったジム・フューリック(米)とブライアン・デービス(英)は延長ひとホール目の第二打で決着が付くという珍しい幕切れに終ったが、ゴルフ史に残る美談になるのではないか。恐らく会場の観客は何がなんだか分からないうちに試合が終わり、ゴルフを知らないテレビ観戦者は何が起きたかも理解できなかったに違いない。
延長ひとホール目は最終18番ホールで行われたが、18番ホール左サイドは海岸で、グリーンの左側もそのまま砂地に雑草が生えたハザードになっている。ピンは危険な左サイドに立っており、デービスはセカンドショットを積極的にピンを狙っていったが、僅か左にそれて海辺のハザードに落としてしまった。優勝経験豊富なフューリックは、ピンに遠い右サイドの安全な場所にボールを運んだ。もっぱら観客の関心はデービスのボールが打てる場所にあるかどうかだったが、テレビカメラがアップした様子では、雑草と枯れ枝の間にあるボールは何とか打てそうである。数分間観察したデービスは意を決して、ピンの方向に難しいショットを敢行した。ピンより少しオーバーしたが難しいショットを成功させて観客は万雷の拍手を贈った。しかし当のデービスは深刻な顔をして競技委員を呼んで何か言っている。競技委員はトーキーで大会本部と何か話し合っている。フューリックも観客も何がなんだか分からない数分間の静寂が続き、やがて競技は続行された。フューリックが第三打をカップから数十センチに寄せたあと、デービスは第四打を打った途端歩きだしてヒューリックに握手を求めた。ハザード内で枯れ枝に触れたとして自ら二罰打を課したからだ。
ゴルフの神髄は「あるがままに打つ」ことと「自己審判制度」にある。違反行為は自ら判定して自分を罰しなくてならない。ゴルフ規則によればハザード内でアドレスしたときクラブヘッドは何物にも触れてはならず、違反すれば二打のペナルティーを課さなければならない。デービスのハザードからの第三打は誰の目にも鮮やかなショットだったが、デービス本人は「打つ時に何かに触れた」と主張して止まない。呼ばれた競技委員は大会本部に連絡を取り、テレビ局のカメラを再生してデービスの主張を証明したようだ。対戦相手のヒューリックが何も言わないのに、デービス自身が自分の違反を証明させて自ら敗北を決定した珍しい出来事であったが、それは久し振りにゴルフの神髄に触れる爽やかなフェアプレーとして世界中のゴルフファンを感動させた。
2010年マスターズで韓国勢の活躍は素晴らしかった。アンソニー・キムは米国籍ではあるが、彼も含めると上位10名中3名が韓国人だった。彼らは強いだけでなくプレーマナーの良いことと、常に堂々としていることに感心させられる。彼らは何処で何を学んであのようなプロになったのか興味は尽きないが、K.J.チョイなどは敬虔なクリスチャンで、ボビー・ジョーンズと同じように常に「祈りの人」であることは良く知られている。そのK.J.チョイが米国中から集中砲火をあびた手負いの虎・タイガー・ウッズを四日間にわたり影武者のように支えた姿は、まさに「騎士道精神」を感じさせる美談としてマスターズ史に残るのではないか。
偶然か神の哀れみか、傷だらけのタイガーは米国ツアーでも屈指の人格者といわれるK.J.チョイと四日間プレーできてよかった。予選二日間は委員会の配慮があったとしても、決勝ラウンドは成績順に組み合わせが決まるから、よほど実力があるか神の意志が働かない限りありえないことだ。三日目が終ったとき、最終日もK.J.チョイと回ることが決まって、タイガーは本当に嬉しそうな顔で握手を求めていたが、表情は孤立するタイガーの心境を表わしているようにもみえた。PGAツアーは何といっても未だ白人中心社会であるから、アジア・アフリカの混血タイガー・ウッズに対する風当たりは相当強いはずである。同じアジア人のK.J.チョイが、タイガーの風除けのようにして堂々とプレーする姿と毅然とした態度は、まるで風神・雷神のようにも見えて頼もしくも思えた。
ミケルソンに対する万雷の拍手とスタンディングオベーションはマスターズという舞台にふさわしいものだった。ウッズに対する冷静な拍手はマスターズの歴史と伝統に支えられる品格を感じさせるものだった。K.J.チョイはサンデーバックナインに入って優勝するかもしれない勢いを見せたときには少し注目されかけたが、多くはウッズの脇役として時々画面に映る程度だった。今回のマスターズでK.J.チョイが果たした役割をどれだけの人が評価したか分からないが、彼に絶大な拍手を贈り心から感謝したのはタイガー・ウッズではなかったかという気がしてならない。もし映画祭のように助演賞が与えられるとすればK.J.チョイが最有力候補になるだろうが、一見スキャンダルに汚されそうになった2010年マスターズも、例年に負けない内容のトーナメントとして幕を閉じた。21世紀はアジアの時代といわれているが、今後アジア太平洋ツアーを支えるのは日本のプロではなく、韓国のプロに違いないという印章を強く受けたのは、私一人ではなかったかもしれない。
2010年度マスターズはフィル・ミケルソンが16アンダーで優勝したが、今年のマスターズはむしろゴルフ以外の面で大きな関心が寄せられていた。
今年になってタイガー・ウッズの不倫問題が発覚し、大変なスキャンダルとなって世界中大騒ぎとなり、しまいにゲームソフトまで売り出される始末。たまりかねたウッズはマスターズまで全試合を休まざるを得なかったことは、ゴルフをしない女子供でも知っていた。ゴルフ帝王タイガー・ウッズのスキャンダルは米国大統領クリントンのとき以上に大騒ぎだったかもしれない。
一方フィル・ミケルソンは典型的な白人プロテスタントで、真面目なうえ家族を大切にすることで知られている。奥さんがガンと闘っており、昨年からピンクリボンをつけて試合に出ていたが、多くのプロ仲間もピンクリボンをつけて奥さんの回復を祈ってくれていた。アメリカゴルフ界の多くの白人たちは、黒人タイガー・ウッズに王座を奪われて、白人ミケルソンに何とか王座を奪い返して欲しいと思っていたはずだ。ウッズとミケルソンは米国でも人気を二分するライバル同士のうえ黒人と白人、不品行と品行方正、仏教徒とキリスト教徒という具合に余りにも対照的だから本人同士以上に周囲の関心が高まったのは無理のないことといえる。
アメリカの白人社会、特にプロテスタント社会にとって、ゴルフは聖地セントアンドリュウスから伝わる神聖なるゲームであるがゆえに、異教徒や異民族に汚されることは不愉快千万なことなのだ。モンゴル人朝青龍に日本の伝統思想や横綱の名誉が汚されたとして大騒ぎした日本と同じ問題と考えられる。米国によらず世界がグローバル化して、異教徒や異民族が同じ社会で生きてかなければならなくなると、こうした問題が次々起こり対応を誤れば紛争や戦争に発展しかねない。
マスターズが始るまでは試合の途中何かハプニングが起きやしないか心配する人も多かったが、知る限り何事もなかったようだし、マスターズではパトロンと呼ばれる観客も素晴らしいマナーで試合を盛り上げていた。ミケルソンはもちろんウッズにも惜しげない拍手を贈り、ウッズ自身「私を温かく迎えてくれたパトロンの皆さんに感謝します。」と語っていた。ミケルソンが優勝して安堵した人も多いだろうが、本当は一番安堵したのは優勝できなくても無事復帰できたタイガー・ウッズ自身だったに違いない。