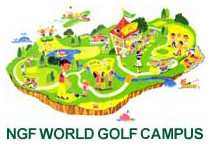大物ルーキーと言われる松山英樹が、プロ転向して早くも大物振りを発揮しているが、同じ歳の石川遼が米国ツアーで悪戦苦闘している姿と対照的だ。しかし石川遼もデビューした時には大物ぶりを発揮して世間をアッと言わせたものだが、その石川遼が世界に出て苦しむさまに、世界の壁の厚さを知って私たちの方が驚いている。ならば世界の壁はそんなに厚く、日本のゴルフ技術はそんなにレベルが低いのかと思いがちだが、私は断じてそんなことはないと信じる。
ゴルフは登山、スキー、マラソンなどと同じように気象条件や自然環境に対応しなければならないスポーツだから、環境が変われば技術だけでは勝てない。
そのうえゴルフは自然環境だけでなく、社会環境にも対応しなければならない厳しい側面を持っている。石川遼は日本PGAの閉鎖的封建社会の殻を破って頭角を現し、米国に渡って新たな社会環境に挑戦している。自由平等を国家理念とするアメリカ合衆国にあっても、白人プロテスタントが支配する米国PGAという社会環境は宗教色の強い差別社会でもある。かつてリー・トレビーノ、チチ・ロドリゲス、ロベルト・デビセンゾが、いまはビジェイ・シン、タイガー・ウッズ、アンヘル・カブレラらが目に見えない宗教や人種の壁と闘っていて、石川遼もそのひとりで、置かれた立場を思うとやはり「頑張れ!」と叫びたくなる。
慣れない自然環境に飛び込んだとき人の体は異常な反応を示すが、慣れない社会環境に飛び込んだときは、むしろ体より心の方が異常な反応を示してしまう。そのうえ人の体と心は微妙に連動しているので、異常反応が連鎖を起こして自分自身でもコントロール不能の状態に陥ってしまう。かつて多くの若者をアメリカゴルフ留学に送り出したが、SOSの連絡を受けて何度も救出に行った経験がある。「朝になると足が動かなくなって一歩も歩けない」とか「英語が分からないから買い物にも行けない」といって閉じこもっている。もっと進むと「もう日本には帰れないから自殺したい」と訴える。このような社会環境に対する反応は、その社会に順応するか無視しなければ耐えられない。有色人種が白人社会で生きるのも、無信仰者が異教徒社会で生きるのも、社会環境の違いは私たちが生きるうえで実に大きな壁だ。地方人が東京に来ても、東京人が地方に行っても、それぞれの社会環境の違いは大きな壁になる。その壁を乗り越えた人だけが異なる社会環境で生きていくことができるし活躍することもできる。ガラパゴス島といわれる日本もどんどんグローバル化して、いろいろな人種、国籍、宗教の異なる人々が住みはじめた。観察すると外国からガラパゴス島に来た人には住み心地が良い環境のようだが、ガラパゴス島から外国に行くとどうにも住み心地が悪いようだ。ガラパゴス島の住人は異質な社会環境に住めなくなってしまったようだが、世界で活躍しようとするなら、ガラパゴス島を飛び出してどんな社会環境にも順応できる体質を作らなくては駄目だ。実際に野球やサッカー、技術者や芸術家は、どんどんガラパゴス島を飛び出して活躍しているではないか。ただし、ガラパゴス島固有の甘ったれ精神は置いていかないと命取りになることだけは肝に銘じておかなければならない。代わりに世界に通用する武士道精神をまとって行くことを是非お勧めしたい。
文部大臣の指導資格認定証はゴルフ界にもある。日本プロゴルフ協会が発行するインストラクター資格には時の文部科学大臣の名前がデカデカと書いてあるから有難い免許皆伝に違いない。しかしゴルフは世界中で行われているスポーツだし、とっくの昔に国際化しているはずだから、今さら日本国文部大臣認定もなさそうだ。リオデジャネイロ・オリンピックから正式種目に採用されるから、いよいよグローバル化といえるが、その前提条件として世界統一基準や統一規則が採用されたことがあげられる。競技をつかさどる規則は米国USGAと英国R&Aによって世界統一されているし、コースの難度査定やプレーヤーの技量評価もUSGA基準によって世界統一されている。最も大切なプレーヤーの養成や育成は独自の創意工夫や研究努力,それをサポートするコーチの能力に委ねられている。欧米諸国は勿論、中国や北朝鮮でもゴルフコーチの国家認定制度や行政保護政策などないが、日本では文部省が競技団体や指導者団体を行政管理下に治め、保護規制によって自由活動を制限している。「文部省公認団体は外国技術ノウハウの導入を禁止する」「文部省の認めない団体に加担協力したものはプロ資格を剥奪する」「文部省の認めない機関の教育を受けたものは、アマチュア資格喪失の原因となる」等々。日本の社会構造は国際化された自由な世界と思われているスポーツ界ですら、実は行政の統制下にあって民間の事業活動が規制されたり制限されている。以前から「構造改革」や「規制緩和」が叫ばれているが、実態や現実を分かっている人は政治家やマスコミも含めて極めて少ない。相撲協会や柔道連盟と同じようにゴルフ団体の構造や規制についても、実態が分かっている人は殆どいない。
TPP交渉参加の意味は、幕末に欧米列強から通商条約の批准を求められたのに良く似ている。日本に住んでいると日本は何でもできる自由な国に思えるが、実は規制や制約が多くあって、新しいことや革新的なことは何も出来ないガラパゴス島であることに気がついていない。「井の中のカワズ、大海を知らず」という諺があるが、日本ガラパゴス島に住む日本人には世界の実態が分からない。「知らぬが仏」という諺もあるが、知らないことによってかえって平和でいられることも多いから知ろうとしないのかもしれない。日本で土日祭日にゴルフをしようと思えば、近郊ならメンバーに頼んで高いビジター料金を払うか、近県なら高い高速道路料金と平日の五割増料金を払わなければならない。どっちが安くつくか考えさせられるが、欧米豪州カナダでは想像もできない実態なのである。土日祭日料金が高いことも、18ホールプレーするのに200ドル300ドルもかかることも、高速道路をたった2,3時間走って何千円もかかることも、娯楽施設利用税が掛かることも、子供料金がないことも、公営ゴルフ場も民営ゴルフ場も同じ料金体系であることも、全てガラパゴス島固有の実態なのである。外国でゴルフをした人や高速道路を走った経験がある人は多いはずだが、なぜこんなにも違うのか疑問に思う人が少ないのも不思議なことだ。ここは日本だからと簡単に割り切ってしまうようだが、日本と外国は違うのが当たり前と考えているのかもしれない。日本と外国では違っていて当たり前なことと、同じである方が当たり前のことを協議する場をTPPとするならば、一刻も早く参加した方が良いに決まっている。誰にとって良いかといえば国民や大衆にとってであり、ゴルフに関するならば一般大衆ゴルファーにとってである。決して特定業者、特定団体、特定議員、特定役人にとってではない。
2年ほど前に相撲協会の体質が問われて大騒動したが、今度は柔道連盟の体質が問われて大バトルが始まった。相撲も柔道も日本の伝統スポーツ文化としての歴史を持っている。今では横綱も優勝者も外国人力士が独占しているし、モンゴル出身の力士が圧倒的に強いのをみても国際化したことは明らかだ。それならモンゴル相撲と日本相撲が同じ格闘技かというと実際には大分違うし、欧州出身の力士はレスリングやサンボなど全く別の格闘技から転向しているようだ。だから相撲の場合には相撲が国際化したというより、力士が国際化したというほうが正しい。相撲興行は日本国内だけで開催されているから国際化したとはいえないが、ウランバートル場所とかモスクワ場所、パリ興行とかニューヨーク興行が開催されるようになれば本当に国際化したといえるだろう。
相撲に対して柔道は完全に国際化している。世界中いたるところに柔道場があり、世界各国に柔道協会があるうえ世界柔道連盟という国際組織まである。さらに世界統一ルールに従って世界選手権やオリンピック大会が開催されているから、国際化を超えてグローバル化したといってもよいのではないか。つまり同一基準に従って地球規模で行われているからグローバル化である。ところがどうも最近明らかになってきたことは、日本の柔道界の実態が古式豊かな伝統技芸の姿を残したまま存在していて、国際社会どころか現代社会そのものに受け入れがたい状態のようだ。これをガラパゴス化というが、密閉された閉鎖社会で行われている古き慣行は、その世界で常識であっても一般社会では非常識を超えて犯罪行為なのである。事情聴取を受けたり逮捕された関係者に全く責任意識がないところに更なる問題の深さが感じられるのだが。
実際に柔道の試合を見ていると、外国選手の闘い方は「エッこれ柔道?」と思うことが時々ある。柔道ってもっと堂々としたもの、礼儀正しいものという先入観があるから違和感を感じるのだが、私の錯覚なのだろうか。この度の騒動は指導員や指導現場から発生したものだが、彼らはみな日本柔道連盟と文部科学大臣が認定した指導資格認定証を掲げている。それでは外国で指導している指導員たちも日本の文部科学大臣の認定証を掲げているのだろうか。そんな話は聞いたことがないし、他にも不思議に思うことがある。鍼灸治療院や整体治療院には、日本柔道連盟と厚生労働大臣が認定した接骨治療師の認定証が掲げてある。接骨治療師が柔道を指導しているとも思えないし、レントゲンも手術室もない治療院で、交通事故や工事現場で起きた複雑骨折の治療ができるとも思えない。果たしてそれを日本柔道連盟や厚生労働大臣が認可して問題ないのだろうか。なにやらウサンクサイ気がする。大臣認定の資格認定証は他にもいっぱい存在するが大丈夫だろうか。TPPの交渉が今年から始まるようだが、国際化からグローバル化に進もうとする時代にあって、日本固有の構造や制度規制を大局的に見直すチャンスではないか。日本固有の伝統文化ならば是非とも守るべきだし、政界・官庁・業界団体の癒着から生まれた利権構造ならば一刻も早く構造改革して規制緩和し、外部の優れた技術や人材を受け入れた方がいいに決まってる。構造改革、規制緩和、TPP参加という言葉の意味はとても深いということを頭に入れておこう。
スポーツの世界はどんどん国際化し、日本の国技である相撲さえも開放政策を採らざるを得なかった。その結果、蔵前国技館に日本人の優勝力士像がなくなった。しかし、やがて世界中から力士を目指して人材が集まり、世界中に大相撲中継が流されるようになるだろう。日本固有の文化を求めて世界から人が集まり、その情報がまた世界に流されていく。世界の人々は髷を結って着物を着こなし、礼儀正しく振舞う姿にサムライの文化を見るかもしれないし、武士道精神を理解するかもしれない。既に柔道は世界に広まりオリンピック種目までなっているが、日本の武道は世界の人々にとっても魅力あるスポーツ文化として受け入れられたからに違いない。武道だけではなく茶道も華道も世界中に広まっているが、日本の文化として広まったことが素晴しい。
ご承知のとおりゴルフはスコットランドに発祥し、アメリカはじめ世界に広まった。欧米カナダ豪州には文化として広まったが、日本には商業娯楽として広まり文化の香りが消えてしまった。日本の若者はゴルフに余り関心を持たなくなってしまったが、日本のゴルフの姿に文化性より不健全性を見てしまったからではないだろうか。「贅沢ゴルフ」「接待ゴルフ」「会員権破綻」など、若者の判断のほうが正しい。もしそうだとすると、日本のゴルフに文化性を回復させるには相当の時間と努力を必要とする。若者の目に魅力的に映るには見せかけの文化ではなく本物の文化でなければならない。それは理屈ではなく感覚的な魅力だから、衛星放送などによって世界の檜舞台で展開される国際試合を観ることによって変化するかもしれない。日本の選手が国際試合で活躍する姿は何よりも効果があるが、そのとき日本の選手が欧米諸国の選手に見劣りするようでは逆効果だ。身長や飛距離の問題ではなく風格や品格の問題なのである。
日本には長い歴史と伝統に支えられた固有の文化がある。その文化を創ってきた日本人を支えているものは武士道精神といわれ、日本人の風格や品格を形成してきたともいわれている。ゴルフが国際化していく中で、日本のゴルファーが欧米諸国のゴルファーに堂々と伍していくには、武士道精神で武装するのが手っ取り早い。なぜならば欧米諸国のゴルファーは騎士道精神で武装しているからである。武士道精神は一級の風格と品格を備えているから、世界中どこに行っても通用する。日本のゴルフには風格も品格もなくなってしまったが、日本のゴルファーはいつでも武士道精神によって風格や品格を備えることができる。野球やサッカーはサムライを名乗って国際試合に臨んでいるのだから、ゴルフもやがてサムライを名乗って国際化に臨んで欲しいものだ。
日本でゴルフのプロというとトーナメントプロとレッスンプロを指すが、欧米豪州カナダではクラブプロやビジネスプロを指す。ゴルフ大国アメリカには何万人ものゴルフプロがいるが、そのうちトーナメントプロはせいぜい1000人前後、レッスンプロはほんの僅かしかいない。「えっ!」と思うかもしれないが、日本のゴルフ界の構造が欧米諸国と根本的に異なる点のひとつなのだ。ゴルフの分野だけでなく、いろいろな分野で日本の特殊性が明らかになってくるだろうが、それがグローバル化の特徴でもある。今年はTPP交渉参加の是非を国民レベルで検討しなければならないが、私たち国民一人一人が自分本位や日本の国益本位で物事を判断する訳にはいかない時代が到来したということだろう。
幕末の時代に鎖国によって徳川幕藩体制を守ろうとした人々も、外国人を獣のように毛嫌いした人々も、そのとき世界で何が起きているのか、欧米諸国はどうなっているのか知らない人たちだった。アメリカでは独立戦争が終わり自由平等を掲げる民主国家が成立していたし、フランスでもフランス革命が終わり自由平等博愛の理念の下に共和国が成立していた。幕末の若者は吉田松陰に象徴されるように、処刑されることが分かっていても自分の目で世界を見たかったのだろう。若者の好奇心と情熱が時代を変え社会を変えていったことを思うと、日本の構造改革や規制緩和が一向に進まずどんどんガラパゴス化していくのはなぜか、まことに不思議なのである。もし日本の若者がいまの日本に満足して現状維持したいと考えているならば、それこそ天下泰平というべきで何も言うことはない。しかし現実は学校卒業しても仕事がない、結婚したくても家庭が支えられない、子供が生まれても育てられない。ましてゴルフがしたくても余裕がなくてできない。いま世界で何が起きているというのだろうか。
世界はいまグローバル化に向けてまっしぐらに進んでいる。ヒト・モノ・カネが国境を越えて自由に移動する時代が到来したのだ。街に出れば外国語を話している人が一杯いるし、店をのぞけば外国産の商品が一杯あふれ、銀行に行けばいろいろな外国紙幣が交換されている。やがて自分は何処の国で暮らしているか分からなくなるかもしれない。そんな世の中で日本のプロだけが日本固有の姿で存在していることを誰も疑問に感じていないようだ。欧米諸国のゴルフ場はほとんど全てプロが経営しているのに対して、日本ではプロが経営しているゴルフ場はほとんどない。ゴルフ場はトーナメントプロやレッスンプロでは経営できないから、欧米諸国では大学やビジネススクールでクラブプロやビジネスプロを養成している。欧米諸国はどうなっているのか知らないとすれば、日本のゴルフ界の人たちは幕末の人たちとなんら変わらないことになってしまう。
「ゴルフに基本はない」。この一言は私の頭にこびりついて離れなかった。私は学生時代に「柔道」「剣道」「弓道」「合気道」「書道」など手習い程度の指導は受けていたが、いずれの道場でも師範から「守破離を大切に」といわれ続けた。
「守」とは基本を忠実に守ること。「破」とは基本を破ること。「離」とは基本を超越することと教えられた。「書道」ではまず楷書を習い、文字のカタチが整ってきたところで行書を習い、草書は当分先の話だとされた。案の定、70歳にして未だに草書は満足に書けない。基本を離れ「動けば即技」の境地に達するのは容易なことではないことは理解できた。
1970年代の日米三強といわれた六人のスイングが全く違うのは、それぞれみな基本を超越した「動けば即技」の境地に達した達人たちだったからに違いない。達人の域に達するには毎日朝から晩まで何年間もボールを打ち続け、試合という緊張場面で失敗を重ねながら挫折を乗り越えていかなければならない。もし本当に基本がないとすれば初心者はその達人の技から何を学ぶというのだろう。ところが驚いたことに、ゴルフをしたことがない子供は、実に巧みにトッププレーヤーのスイングを真似するではないか。ならばそのスイングでボールが打てるかというと、その子もやはり初心者の球しか打てない。米国の学校体育にゴルフが導入されたとき、まず最初に基本テキストや基本マニュアルが作られたことが実に良く理解できる。
「女性ゴルフ教室」の指導現場はどんな状況だったか。いわゆる主婦といわれる中高年女性が14人打席に並んで、全員7番貸クラブでボールを打っているが、中には最初からかなり強いスイングができる人もいる。おそらくテニスか何かスポーツを経験したに違いないが、ボールが打てないことには変わりない。中に全くスポーツ経験がない女性もいたが、クラブを振る姿はおしとやかで日本舞踊のお稽古に近かった。ゴルフスイングという体の動きそのものが全く分からないうえに、クラブを振り回す握力がない。しっかり振ってと激励されると、よろけて3階打席から転落しそうになる。プロはあわてて飛んでいって体を支え、跪いてグリップの握り方を丁寧に教えるが、グリップを教えるとますますスイングが怪しくなってよろける。「指導に当たって女性の体には絶対に触れてはならない」という私の厳命は全く意味を成さないものになってしまった。
それから数年後、米国NGFの指導マニュアルに「スイング動作を知らない初心者に最初からボールを打たせてはならない。最初は何も持たずに体にスイング動作を覚えさせる。次にクラブを逆さまに持ってクラブヘッドの重さを感じさせないでクラブの振り方を覚えさせる。次にボールを打たずにクラブヘッドを振る感覚を覚えさせる」と書いてあることが分かった。そういえば学生時代に友達を投げ飛ばしたくて勇んで講道館に通ったら、三ヶ月は投げ飛ばされる稽古ばかりでうんざりしたが、この基本指導をゴルフでは『ドリル』といい、柔道では『受身』といって大切にしている。
小中学生の頃は何かに付け「人のせいにするな」、高校大学の頃は「怪我と弁当自分持ち」と言われ続けてきた。当時は余り意味が分からず当たり前に受け止めていたが、今になって振り返ると常に「自己責任」を問われ続けていたのかなと思う。小学校低学年の頃は小田急線上り下りとも30分に一本しか多摩川鉄橋を通らなかった。登り電車が通過した後、悪ガキ3人で鉄橋を渡り始めたところ中間地点に来て、レールからカタンコトンという車輪の音が聞こえ始めた。振り返っても電車の姿は見えないが、間違いなく電車はこちらに向かってくる。想定外の出来事に一刻も早く鉄橋を渡りきる以外に手はないと、脂汗を流しながら枕木を一本一本踏みしめるが、歩くには丁度いい歩幅が急ぐといささか狭く足を踏み外しそうになる。それまで何とも思わなかった眼下の多摩川の流れが急に恐ろしく思いはじめた。とうとう渡り切らないうちに追いつかれてしまったのだが、想定外の電車は妙な格好をした巡回修理車だった。脂汗を流して鉄橋にしがみついている悪ガキに向かって運転手は「死んだらどうする!」と一言叱りつけて行ってしまったが、当時の大人は全員が戦災を生き延びた人だから、子供に対しても自分の命は自己責任で守れと叱ったのだろう。
OBを打つと「フェアウェイが狭すぎるよ」、バンカーからホームランすると「砂が入ってないよ」、3パットすると「グリーンが悪いなあ」、スコアが悪いと「トリッキーなコースだなあ」全てコースのせいにしたいのが人情だ。ゴルフでは失敗の言い訳がゴマンとある。「打とうとしたら人が動いた」「一緒に回った人のマナーが悪くて」「キャディが新米で」「後ろの組に打ち込まれて」「前の組が遅くて」などは、人のせいにした言い訳。「新しいクラブが合わなくて」「Sではシャフトが硬すぎて」「いつも使うボールじゃないので」「今日のグリーンは自分に遅すぎて」「ディボットだらけで」などは、道具やコースのせいにした言い訳。「最近練習していないから」「仕事が忙しくて」「昨晩遅かったので」「少々バテ気味で」「歳のせいかアチコチ痛くて」などは、自分自身の言い訳。そんな言い訳だれも聞いちゃいないし自己責任にもならない。
言い訳を言うのはまだ良いほうで「ボールを頻繁に動かす」「ドロップしないで放り投げる」「ピックアップしたボールを元の位置に戻さない」「打順を守らない」「OKパットはノーカウント」などは、違反の意識すらないから言い訳もない。最もタチの悪いのは承知のうえで黙々と違反をする人だ。誰も見ていないと「ライを改善する」「ボールを動かす」「替え球を打つ」「ハザードにソールする」「ストロークをゴマかす」などは、自己責任とはいえ人間性を疑われ信用すら失う。
子供なら「一生疑われたらどうする!」と厳しく叱ってくれる大人がいるだろうが、大人になると誰も叱ってくれない。全てを「自己責任」として一身に背負わなければならないとは、実に重いペナルティーだ。
セルフプレーは人間の文化だと思う。論語に「小人閑居して不善をなす」とあり、聖書に「義人はいない一人もいない」とあるように、どうやら人間の本質はイイカゲンらしい。そのイイカゲンな人間に審判を付けずに自己責任でマジメにプレーせよというのがゴルフの本質である。私自身ゴルフを始めて間もなく自分に内在するイイカゲンさを思い知らされた。自宅の裏にあった米軍コースに頼んで早朝練習をさせてもらっていた頃、一人でプレーしていると「アッ、この一打はなかったことにしよう」「コレ、ノーペナでいいよな」「今のは本来の自分じゃない」。次から次へとゴマカシとイイカゲンが連鎖して、ついには自己嫌悪に陥ってしまった。論語や聖書に書いてあったことは訓戒ではなく事実だったのである。
ゴルフがなぜセルフプレー・セルフジャッジを原則とするのか研究するうちに段々とキリスト教プロテスタント思想に基づくからだと分かってきた。自分を含めて誰もが、人はごまかせても神をごまかすことはできない。人間は誰もが全知全能の神の前に一人で立って清廉潔白を証明することはできない。セルフプレー・セルフジャッジは神の審判のもと、自分自身がフェアにプレーすることを前提に成り立っている。それを知ったら誰もが「コワッ!」と思うはずだ。
セルフプレーではティーショットとパット以外、ほとんど誰も見ていないところでプレーする。ボールが多少動いても、多少動かしても自分と神さま以外は誰も分からない。その自分と神さまが協同審判を勤めるルールになっているのがゴルフゲームなのである。公式競技のように自分を監視するマーカーや競技委員がいないセルフプレーでは、スコアをゴマカシてもイイカゲンなルール裁定をしても、同伴競技者はお互いの自己申告スコアを受け入れざるを得ない。
「おかしい」と思っても、ほとんどの人が黙って受け入れるのは、言い争って自分のゴルフを台無しにしたくないからである。ズルイゴルファー、イイカゲンゴルファーは仲間うちで有名だが、本人だけは自覚もなく自分はマジメゴルファーと思っているところがコレマタ実にコワイ。
セルフプレーがまともにできない人は恐らく普段の生活もイイカゲンでゴマカシが多いに違いない。だからそういう人とは余り深く係わらない方がいいし、ビジネスはしない方がいい。あとできっと後悔する。セルフプレーにはそれほど重い意味があるのだから人件費節約とか経営合理化という経営サイドの都合や、サービス低下とかパブリック化という顧客サイドの視点で判断してはならない。ゴルフに対する姿勢はその人の人生に対する姿勢そのものだから、プレー姿勢を見ているのは自分と神さまだけでなく、実は同伴競技者となった仲間が最も厳しく見ていることを決して忘れてはならない。クルマの運転もゴルフのプレーも自己責任によるセルフプレーだから、性格のみならず人間性まで物の見事にムキダシにしてしまうのだ。
「お座敷ゴルフ」という言葉を聞いたこともない人が増えてきたに違いない。これぞガラパゴス化の代表といえるかもしれないが、日本のゴルファーを決定的に駄目にした根源なので多くの人に知ってもらいたい。そもそも「お座敷」が日本固有の文化だから外来スポーツ文化のゴルフと馴染むわけないが、見事に融合させたところに強烈なインパクトがある。「お座敷」はもっぱら政財界人の商談の場、密談の場として利用されてきたが、それ以前は旦那衆の遊びの場として利用されていた。遊びの場を商談の場、密談の場として利用するとはスマートといえばスマート、ウサンクサイといえば限りなくウサンクサイ。評価はともかく日本の経済成長に大きく貢献したことは事実なのだ。
しかし、日本のゴルフ文化にとっては成長どころか堕落に貢献した。そもそもゴルフは遊びにしろ競技にしろ自己責任・自己審判を大原則に成り立っている。エチケットから始まって状況判断・クラブ選択・結果責任・規則裁定を全て自己責任で進めなければならないのがゴルフだが、その大半をキャディに委ねたのが「お座敷ゴルフ」の姿だ。お座敷なら仲居や芸者が果たす役割をコースではキャディが一手に引き受けてくれる。OB・バンカー・距離・目標・風向・安全確認から、クラブ選択・ルール裁定・処置方法、さらにはボール探し・バンカーならし・グリーン修復・パットライン指示・旗ざお持ち・ボールマーク・ボール拭き、おまけに慰めと励ましの言葉もかけてくれる。
欧米豪州なら大統領といえども全てを自己責任で実行するが、それをセルフプレーという。いい加減なことをすればゴルファー以前に人間性や大統領の資質まで疑われる。お座敷ゴルフで育った日本のゴルファーは欧米諸国の人とまともにゴルフはできない。特に政財界のみならず民間の要人ともゴルフはしない方がいい。交流以前に人格を疑われては元も子もない。日本のゴルフがガラパゴス化していることは、外部環境に触れて初めて分かることだが、ガラパゴス島で育ってしまうと結構居心地が良くて「コレはコレでいいんじゃない?」と思ってしまうところが落とし穴だ。
周りの空気が読めない人のことを「KY」と言うらしいが、今や日本全体が外国からKYといわれているような気がしてならない。ゴルフエチケットの基本理念は 1.安全に対する配慮 2.他のプレーヤーに対する配慮 3.コースに対する配慮と全て周りの空気を読むことばかり。お座敷ゴルフはその全てをキャディに委ねてしまったところに問題があった。キャディ教育ばかり熱心にして肝心のゴルファー教育をしてこなかったことは、ゴルフの基本精神からしても本末転倒だった。しかしゴルフは自己責任・自己審判のゲームである以上、ゴルファーひとり一人が自己責任で自分を教育しなければならないことも確かだ。
欧米豪州でゴルフをした人はアウトとインの中間で昼食休憩を取った経験はないはずだ。通常アウトからスタートして9番を終わり、トイレかショップに用事がない限りクラブハウスに戻ることはない。9番と10番がクラブハウスから離れていることも多いから、トイレはプレー途中で用を足し、お腹が空いたら持参したサンドイッチ、バナナ、チョコレートなどを食べる。移動売店車が回ってきたら買って食べればいいし、愛想の良い売り娘が来たら無理して買って食べても良い。ゴルフはハイキングと同じだから、プレーしながらモノを食べてもエチケットやマナーを問われることはない。アリゾナ当たりでゴルフをするときは、5リットルくらい水を用意しないと生きては帰れない。料金を払ってスタートしたら、後は全て自己判断・自己責任でプレーするのが国際標準のゴルフスタイルなのだ。スターターは「グッドラック」と一言いうだけで、後は一切干渉することはない。
9ホールで1時間休憩し、酒を飲んだりご馳走食べたりして残り9ホールをプレーし、終わったらゆっくり風呂に入る「お座敷ゴルフ」は、日本固有のゴルフスタイルなのだ。日本のコースでは9ホール終わって調子が良いからこのままプレーを続けたいといってもほとんど許されない。問答無用で午後のスタート時間を告げられ、最低40分から1時間の休憩を申し渡される。だから日本のゴルファーは18ホールスループレーする体力も気力も備わっていない。一世代前のボビージョーンズの時代には、一日36ホール競技をしていたから18ホール終わって休憩と食事を取らないと体力が持たなかった。最近は9ホールで充分という人も出てきたが、現代人はそんなに体力が落ちたのだろうか。これは体力の問題より習慣の問題だ。欧米豪州でゴルフをする場合、日本人といえども18ホールスループレーが原則だから、疲れて休みたければ後続組に「少し休みたいので、お先にどうぞ」といえば気持ちよくパスしてくれる。実際には海外のゴルフコースで、途中疲れて休んでいる日本人ゴルファーの姿を見たことがない。疲れるどころか日本でプレーしている時より遥かにハツラツとした姿で、雨が降ろうが雷が鳴ろうが早朝から日没まで頑張っている。だから日本人は現地の人から「カミカゼゴルファー」と囁かれている。
日本固有の「お座敷ゴルフ」がいつから定着したか良く分からないが、私自身も外国人に指摘されるまで気が付かなかった。ただ周りがそうしていることと食堂売上を伸ばすためであることだけは解っていた。その国固有の習慣や環境を常識として受け入れていること自体をガラパゴス化というのではない。ガラパゴス化というのは、その常識が国内でも通用しなくなり絶滅の危機に瀕したとき初めて使われる表現なのだ。やがて「お座敷ゴルフ」を懐かしく思い出す時が来るのだろうが、ゴルフ場の絶滅だけは見たくない。