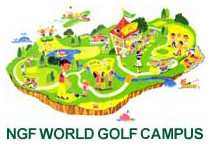何万、何十万にも及ぶ新設ゴルフ場の会員が全国各地で「預託金返還訴訟」を起こし始めたが、今となっては貧者と貧者の泥仕合であり不毛の争いであった。ゴルフ場は本来ゴルフを愛する同志が結束し、資金を出し合って発起人代表に夢を託して建設されるものである。同志から夢を託された発起人代表は預かった建設資金に対して「預り証」を発行し、資金管理を誠実に行うが「預り証」を発行しておかないと税務上「所得」や「贈与」とみなされるからだ。同時にゴルフ場建設には大変な時間が掛かるため「10年据置き無利息」の条件を付けなければ途中で気が変わったから金を返してくれと言われたり、利息を付けてくれと言われたらゴルフ場建設は挫折してしまう。だから本質的には預託金ではなく出資金であり、不正や横領がない限り返還請求する根拠に乏しく、建設を断念したときはじめて残余金の返還を求めるべき性格のものである。
例えば工務店に家の建設を依頼したとき、最初に建設費の1/3を着手金として支払い、工事半ばで1/3を支払い、完成引渡時に残金を支払って建物所有権が移転する。ゴルフ場建設の場合なら最初の出資者である発起人会が出資組合なり社団なり結成して代表者を選任し、資金管理を行うと同時に用地買収作業や工事進捗状況の監督をするべきであった。本来ならパンフレットに名を連ねた政財界の大物や有名人は発起人会のメンバーで、開発会社を監督する立場にあったはずだが、実際は無償で縁故会員になり更に数枚の会員権をもらって人寄せパンダを演じていた。ゴルフ場が完成すれば物件の所有権は出資組合なり社団としてのクラブに引き渡されるべきだが、破綻ゴルフ場にそのようなケースは見当たらない。発起人代表はそのままクラブ理事長となり発起人会はクラブ理事会となったから、会員の権利を護る機関はどこにも存在しない組織ができたことになる。ということは最初から会員の権利地位は曖昧な立場に置かれていて、訴訟になった段階で裁判所に判断を求めても前例主義の日本の裁判所には判例も判断基準もなかったことは言うまでもない。
預託会員権制度そのものが何の法的根拠もないうえ業界固有の制度として定着していたために、商法にも税法にも証券取引法にも抵触しない、いわば法の盲点として存在していた。バブルが崩壊して制度破綻するまでは何の法にも触れずに莫大な資金が集まる、税金は掛からない、使途は問われない、ゴルフを楽しみながら金儲けができるとなれば利用しないほうが間抜けだ。まさに究極の錬金術として事業家も政治家もタレントも便乗したと思われる。70年代以降の日本のゴルフ場建設は実に動機が不純だったために完成後のビジネスにおいても誠実さや真剣みに欠け、欧米豪州の正統ゴルフとは似て非なる日本固有のゴルフ体質が育ってしまった。根底に文化も教養も備わっていなかったことが大きな原因だったと考えられる。文化も教養もない処に突如として経済的繁栄が訪れるとどうなるか、日本のゴルフは深刻な課題を背負っていたのである。
90年代に入るや日銀は突如として金融引締政策をとり総量規制の名の下に新規融資をストップしたからたまらない。ハードランディングという急降下着陸をしたために乗客も積荷も吹っ飛ばされてしまったのだ。建設途上の城は廃墟と化し一国一城の主となったゴルフ場オーナーも兵糧を絶たれて真っ青になった。
会員権発行が打出のコズチだった積りが、コズチを振っても振っても小判は出てこない。「ゴルフ場完成後はビジネスにならない」といわれていたのが現実となってしまったのだ。ギンギラギンのクラブハウスやコースを維持するには莫大な経費が掛かる。来場者とりわけ上客だった社用族ビジターが激減する中でビジネストレーニングされていない有り余る社員をどう取り扱うか、全く解決の道が閉ざされたまま時間だけが経過していった。
時代が逆流し始めると次から次へと想定外の事態が発生してくる。株の暴落に連動して会員権相場が暴落し始めたため、5枚も10枚も会員権証券を持っている人は慌てて売り逃げしようとしたから益々暴落に拍車を掛けることになる。
高額会員権は真っ先に額面割れを起こし、値上がりを見越してローンで買った人は取り返しの付かない事態に陥ったことに顔面蒼白になった。退職金をはたいて買った人、自宅担保で買った人、取引銀行から押し付けられて買った事業経営者など、世界一の金満王国ジパングに何が起きたのか誰も理解できなかったのは当然だ。会員権を買うといえば銀行はニコニコして即日融資してくれたではないか、入会パンフレットには政財界の大物や有名人が名を連ねているではないか。こうしてゴルフに人生の夢を掛けた人たちを目覚めのない悪夢の中に引きずり込んでいったのである。
ゴルフ場側の悪夢も益々恐ろしい事態になっていった。10年据え置きの会員権が次々と償還期を迎え始めていたからゴルフ場経営者は肝を冷やした。60年代、70年代に完成したゴルフ場は預託金額面が安かったので額面割れすることは余りなかったが、80年代に完成したゴルフ場は額面が高額だっただけに軒並み額面割れしていた。悪夢にうなされていた会員権所有者が預託金返還を求めて殺到したから悪夢同士の大混乱に陥ったのである。10年経過したから預託金を返してくれといわれても、お金はギンギラギンのゴルフ場建設に使ってしまったのだから残っているわけがない。銀行からローン返済を迫られる会員と、会員から預託金返還を迫られるゴルフ場との間に仁義なき戦いが始まった。財産形成と夢のような老後のゴルフライフを約束してくれるはずだったゴルフ場オーナーに対して、裏切られたぶん憎さ百倍の集団訴訟が全国各地に繰り広げられていったが、所詮は領主と領民の争いと同じで最後は殺し合いになることは歴史が証明していた。
「ゴルフ場は完成するまでがビジネスで、完成後はビジネスにならない」と良くいわれてきた。確かに宮殿や別荘、公園や庭園で儲けようとして建設する人はいない。どんなにカネを掛けても、それで商売はできない。ゴルフ場は建設段階で大変な作業と時間が掛かるが、そこに多額の資金が動くからビジネスが発生するという意味だ。ではどんなビジネスか。不動産の証券化という新しい金融ビジネスである。米国ゴルフ界の人に預託会員権制度をいくら説明しても皆目理解することはできない。日本の会員制クラブと欧米の会員制プライベートクラブは性質も概念も異なるから根本から理解できないようである。プライベートクラブは宗教信条や価値観を等しくする仲間や同士が資金や責任を負担し合いながら厳格な規律の下に運営されるコミュニティだから、損得勘定で入退会できる組織ではない。日本の会員制クラブは儲かりそうなら入会するし、損しそうなら退会できる。
日本の会員制度は入会金と預託金の二重構造になっていて、入会金は名目どおりクラブ会員になるための費用で退会しても返還されない。一方の預託金は入会条件として付帯する投機証券の性格を持った保証金制度になっていて、10年据置無利息ながら、そのときの相場で売却できる仕組みになっている。金儲けしながらゴルフができる日本固有の金融ビジネスモデルを考案したのである。このシステムは1960年代に考案され、70年代と80年代にブームが起きたが、会員募集という名の証券販売方法は縁故募集・一次募集・二次募集・三次募集・完成募集と通常五段階に及び予定販売金額を事前提示して投機意欲を刺激していたから、ゴルフに興味のない人も金儲けには誘惑された。実際に100万円で買った会員権が500万円になった人、500万円で買って3000万円になった人が現れると、誰だってバスに乗り遅れたくない気分になるものだ。
ゴルフ場建設が本業より儲かる金融ビジネスだとなれば経営多角化の名の下に大手企業まで参入するようになるから、60年代に3億円でできたゴルフ場が70年代には30億に、80年代には300億円になった。本来は競技場であるゴルフ場が金融商品化してからは機能や経済性を無視して見た目の豪華さ、設計者や関係者の知名度などを売り物にするようになった。このような時代背景の中で完成オープン後の経営や採算性など無視したゴルフビジネスが展開されていったが、90年代に入るや一気にそのツケが回り新設ゴルフ場が次々不良資産化して9兆円近い損失を出してしまった。同時に大衆ゴルファーが抱いた財形の夢も泡と化し、第二ユニットの民事再生法によって会員権はゴミ屑のように処理されていったが、金融政策という点火装置に消化装置、民事再生法という焼跡処理装置が用意されたこと、第三ユニットにスポンサーと称するサルベージ屋が待ち受けていたことに気付くのは、外資系ハゲタカファンドが物の見事に大儲けして立ち去った後のことである。
日本でゴルフ場を建設するのは実に大変なことだ。37万平方キロの狭く起伏の激しい島国の日本は、僅か3割の丘陵地に何千万人もの人がへばりつくように田畑を耕して暮らしきたのだから、日本の歴史そのものが領地の奪い合いの歴史でもあった。細かく分かれた田畑は先祖伝来の財産であり、領有権や耕作権をめぐって多くの血と汗が染み込んでいる。ゴルフ場建設に必要な1平方キロを確保するには、何十人何百人の地権者と気の遠くなるような交渉をしなければならない。うず高く積み上げられた土地登記簿謄本の一冊一冊は細かく分筆されているうえ、所有権と借地権、耕作権や入会権が入り組んでいたり、抵当権が設定されていたり、公図と実測図が合わなかったりと煩雑を極める。中にはどうしても地主が分からない土地まである。
大方の地権者から譲渡や借地の了解を取り付けたところで、今度は役所との気の遠くなる交渉が始まる。国も地方公共団体もそれぞれ独立した縦割組織になっているから案件ごとに各省庁の部署をまわり、いろいろ注文をつけられ提出書類がハンコだらけになっても簡単には許認可が下りない。さらに利害関係者の同意を取り付けるには地元有力者、政治家、役人、農協関係者、自然保護団体、市民活動家、暴力団等々モグラ叩きのように交渉相手が現れる。時間は掛かるものの最終的には殆ど金銭解決するから問題ないが、厄介なのは交渉でも金銭でも解決しないゴルフ場建設そのものに反対する自然保護団体や市民活動家だ。しかし何といって最大の問題は資金調達である。駅伝マラソンのように多くのランナーが資金タスキをつないでゴールまでこぎつけているが、途中で資金が続かず破産・自殺・行方不明となって姿を消す人もいる。
ところが驚いたことに80年代中頃から突如として銀行がゴルフ場に積極融資を始めたのである。不動産担保があれば青天井で融資すると言う。今までお百度参りしても簡単に融資しなかった銀行が先方から訊ねてきてゴルフ場開発案件を紹介してくれと言い出したのだ。私が銀行や開発者に米国のゴルフ場建設に関する標準予算や基本概念を話すと化石動物を見るような目で「そんなスケールの小さい計画には融資できません」と相手にされなくなった。そのとき日本に何が起きているのか皆目見当がつかなかったが、日銀が市中銀行を脅迫するようにして仕掛けたバブル経済の序章だったとは崩壊後に知る「後の祭り話」であった。不動産神話を信じ、銀行がいくらでも融資するのを良いことに一件のゴルフ場に何十億、何百億の投資をしてアラビヤ王の別荘まがいのギンギラギンコースを次々と建設したのである。
日銀の金融緩和政策の結果、1980年代後半から91年にかけてジャパンマネーは世界に溢れ出て、英国や米国の名門コースを買い漁るまでに至った。当時は国内の新設コースの会員権募集価格が5000万円の高値をつけていたから、やがて1億円の大台に乗るのではないかと多くの人が思っていた。ところがジャパンマネーの異常事態が恐ろしくなった日銀が急遽金融引締政策に転換したため日本経済は一気に冷え込み社会は大混乱に陥った。特にゴルフ産業は壊滅的な打撃を受けたのである。建設中のゴルフ場は建設資金がショートして工事が止まり、用地買収中のゴルフ場は虫食い状態のまま計画が中断した。会員権の値上がりを見込んでコースの大改造をしたり、豪華クラブハウスに建て替えたりしたゴルフ場は多額の借金を抱え込んだまま立ちすくんでしまった。
国家も企業も人も成長には時間が掛かるが衰退には時間は要らない。逆流現象が起きると次から次へと想定外の事態が発生し、もぐら叩きどころか何もできずに茫然自失の状態に陥る。会員権は売れない、来場者と売上は激減する、銀行は金を貸さないという状態が始まった。更に悪いことに株と共に会員権相場も下がり始めたため、多くの人が慌てて売り急いだから忽ち大暴落へ突入していった。というのは会員権が使用目的で買われているよりも投機目的で買われていたケースが多かったからである。本来ならホームコースの会員権があれば充分なのに一人で5ヶ所も10ヶ所も入会したり、足腰立たない爺さん婆さんまで入会していた。
世の中の多くの人が大混乱しながらも一過性の経済変動に違いないと考えていたから、二・三年もすれば景気が回復して元の成長経済に戻るだろうと予想していた。戦争体験者も撤退どころか「今こそ打って出るべし!」と強気の姿勢を崩さず、子供まで「成績の下落はバブル崩壊によるもの」などと冗談を飛ばしていた。しかし97年に入ると事態はいよいよ深刻になり証券界では100年の歴史を誇る山一證券が倒産し、ゴルフ界では天下の日東興行が倒産した。日本中に死臭が漂い出し、日本の上空には外資系ハゲタカファンドが獲物を探して舞い始めたのである。
NGFはゴルフ界の国際情報機関と見られていたから、私は多くの外資系ファンドマネージャーと接見した。しかし残念ながら私自身バブル崩壊の真相も民事再生法の目的もハゲタカファンドの戦略も良く理解していなかった。日銀は日本経済を護るために、民事再生法は迅速な事業再生のために、ヘッジファンドは不良債権を買い漁るためにあると思っていたが、実態は必ずしも額面どおり単純に判断できないことが時間の経過と共に分かってきた。つまり金融政策・時限立法・外資戦略は始めからユニットになっていた気がするのだ。
ゴルフ再生への道 -1 所有と経営の分離 へ
先週木曜日(2014/03/27)の日経新聞夕刊トップに「アコーディアゴルフ場売却し運営に特化」という記事が掲載された。記事によると現在アコーディアが所有する約130コースのうち、不動産などの権利関係が整理された100コースをシンガポールの投資会社に売却する方針だという。売却したコースはアコーディアがそのまま経営委託を受けてマネジメントを請負うことになるが、この一連の動きを専門的に「所有と経営の分離」という。つまり施設所有者と事業経営者が別れて目的別に機能しようという考えで、解りやすくいえば建物を所有するビルオーナーと建物を借りて事業をするテナントの関係になることを意味する。「なーんだ、そんなことか!」と思うかもしれないが、実は日本のゴルフ界にとっては大変なイノベーションが起きようとしているのである。
日本のコースは1960年代まではゴルフ愛好家たちが倶楽部を結成し、自分たちの専用コースを建設するために資金を出し合って創られたものである。例えば東京ゴルフ倶楽部は米国から帰国した井上準之助が財界の仲間と協力して建設した日本で最初の日本人ゴルフ倶楽部だとされている。基本的には60年代までほぼ同じコンセプトで建設されてきたから、コースは会員の共有財産として健全に運営されていた。会員から信任された理事会は支配人はじめ管理スタッフを雇ってコース管理やクラブ運営を行い、会員に経過を報告し結果に対して承認を仰いでいた。コースが災害に遭ったりコースを改造するには会員に諮って資金を出し合い、共有財産を護ったり価値を高める努力をしていた。
ところが70年代に入るや経済成長に乗じてゴルフブームが起こり、ゴルフ場事業は不動産開発と会員権発行が融合した日本固有の金融ビジネスに変わっていったのである。実体がなくても度胸と地図と赤鉛筆があれば、誰の土地であろうと30万坪を地図上に赤鉛筆で示しゴルフ場建設予定地とすれば、たちまち何億円もの資金が集まって事業家になれた。計画を発表したものはゴルフ場を開発する不動産事業家であり会員権を発行する金融事業家でもあり、成功すればゴルフ場オーナーとなりゴルフ場経営者となりクラブ理事長となって、所有権と経営権と支配権を掌握したゴルフ場オーナー経営者となったのである。三権を掌握したゴルフ場オーナーは一国一城の主であり専制君主でもあった。競って立派な城を築き贅沢を極めたが、男なら一度はなってみたい身分でもあった。私だってチャンスがあれば是非なりたいと思ったものである。しかし専制君主の時代が長くは続かないことは歴史が証明しており、やがて歴史の教訓どおり衰退崩壊の時代を迎えることになる。
ゴルフ再生への道 -2 ゴルフ場戦国動乱期 へ